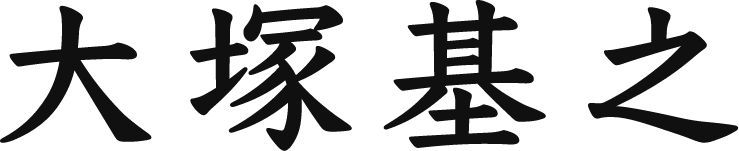greeting
教授挨拶
最適医療の実践と次世代医学の創生
~そしてそのための人材育成
2023年1月から岡山大学消化器・肝臓内科に着任しました大塚基之と申します。ご挨拶をかねて、これから岡山大学消化器・肝臓内科がめざす方向性について、簡単に記載させて頂きます。

- 教授
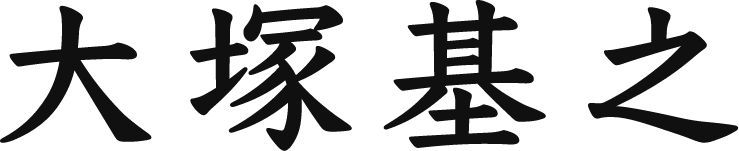
clinic

最適医療の実践と次世代医学の創生
~そしてそのための人材育成
2023年1月から岡山大学消化器・肝臓内科に着任しました大塚基之と申します。ご挨拶をかねて、これから岡山大学消化器・肝臓内科がめざす方向性について、簡単に記載させて頂きます。